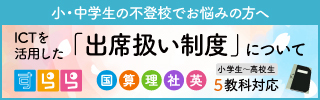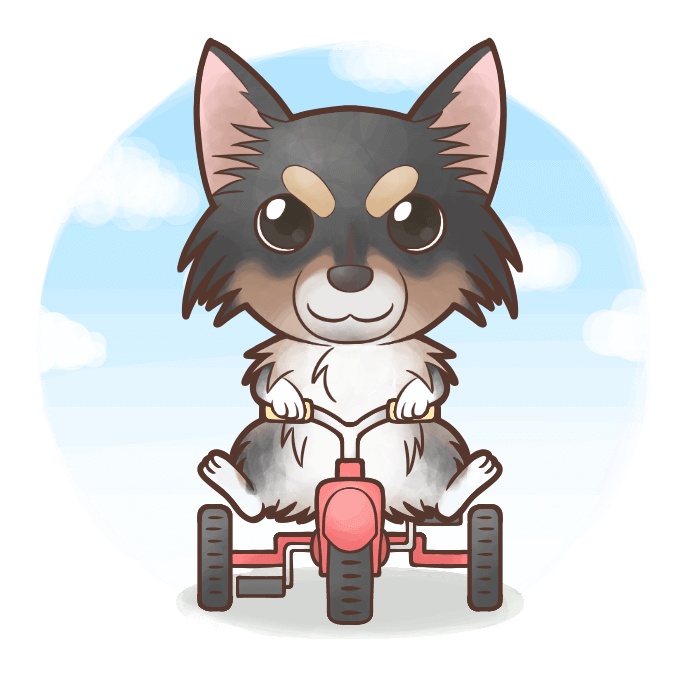心理カウンセラー目線|不登校の子への親の声かけ、自分で決めること
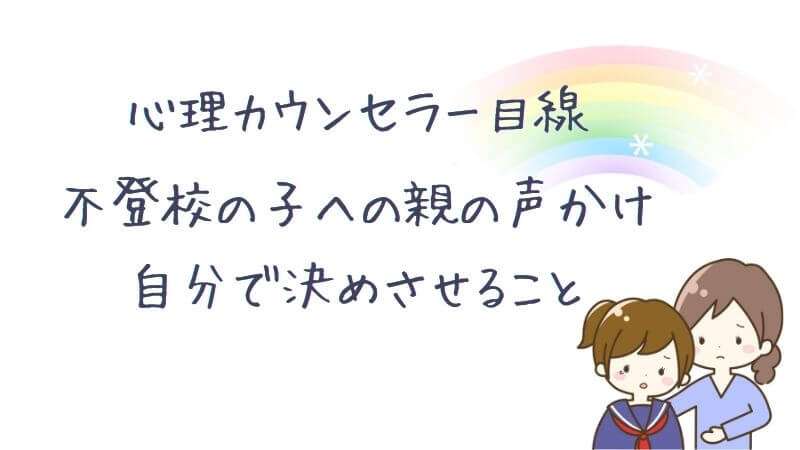
 そら
そらこの記事は、ご自身も不登校経験者であった心理カウンセラーさんに、子どもへの声かけについて聞いてみました。
自己肯定感が大切と言われています。同じぐらい自己決定力も必要です。
今回は「自分で決めること」について語ってもらいました。
子どもが不登校になると、親御さんの多くが不安になり「早く学校に戻れるように」とあせりが全面に出てしまいます。
子どもの将来のためにも学校に行かなくてはいけない、休めば勉強に遅れがでて後々本人が苦労するからなど、子どものためになんとかしようと思います。
もちろん、子どものことを一番身近で見てきたからこそわかることもたくさんあると思います。
今までそんな素振りさえ見せなかったのに、いきなり学校に行かなくなってしまった子どもに対して、心配にならない親はいません。
子どものことを大切に思っているからこそ、必死に説得してしまいがちです。
でも、不登校になっている子どもたちは親が思っている以上に心身ともに疲弊しています。
すでに限界に達していて、学校に行けなくなっています。
今はネット社会なのもあり「不登校」に対しての情報が以前よりも簡単に手に入るようになりました。
不登校になってしまった自分を責め、どんどんネガティブになってしまいます。
それなのに「何があったの?」「お母さんに話して欲しい」など理由を聞き出そうとしていませんか。
ときには不登校になっている子どもに責めるような言葉や感情的な言葉をかけてしまっていませんか。
一番注意しなくてはいけないのが、本人を全否定するような言葉をかけてしまうことです。
子どもが不登校になると、親御さんのなかには自分に余裕がなくなり子どもに思いがけず否定するような言葉をかけてしまうこともあります。
高圧的な話し方をする親だと子どもが自分に自信がもてなくなり、自分の気持ちを言えなくなってしまいます。
子どもは一番の理解者であり味方でなくてはいけない親に否定され、引きこもってしまうこともあります。
子どもが不登校になると親にとっても大変です。
はじめてのことで、どうしたらいいのか戸惑うことばかりだと思います。
不登校で部屋に閉じこもりがちであれば、一緒に御飯を食べに行ったり旅行に行くのもいいと思います。
私が不登校で悩んでいたとき、母が近場の温泉街にいきなり旅行に行こうといいだし、二人だけで行った記憶があります。
お互い無言でほとんど話もしませんでしたが、痛いほど母の気持ちが伝わってきたのを覚えています。
子どもにとって親は常に味方でいてほしいのです。
見守り、子どもが決めたことを尊重、応援しようと思っていても、自分で決められない。
どうしたら「決められる」ようになるのか、悩まれている方もいらっしゃいます。
社会に出てからどうするの?と親御さんにとっても心配になりますよね。
どんな子どもでも自分で決める力を持っています。
では、どうして決められなくなってしまうのかというと、決めなくても済んでしまうような生活にしてしまっている可能性があります。
例えば、なにかトラブルを抱えてしまったとき、親が前に出すぎてしまっていませんか。
子どもが自分で決められない場合、仕方なく親が率先して行動し、なんとか問題を解決させようと「頑張りすぎてしまう」傾向があります。
子どものことを大切に思っているからこそではあるのですが、子ども側からすると、親が一生懸命なのも伝わっていますし、ときにその気持ちが重く感じてしまうこともあります。
自分のことで苦しんでいる姿を見ていると、なんとか期待にこたえようとしてしまったり、自分の意見や考えを持っていても、発言することで傷つけてしまうのではと考え、余計に決められなくなってしまいます。
徐々に自分の気持ちを主張することをやめてしまい、親との関わりや関係性を優先してしまいます。
自分で決められない子どもは、他者を尊重しすぎてしまったり、周囲の和を乱すことを好まず、調和を大切にします。
自分が発言することで周囲の和を乱すなら発言しないほうがいいと考えてしまいます。
子どもは親が思っている以上に、親のことを見ています。
つらそうな親の姿ほど、子どもの心に大きな負担になってしまうことも…。
もし自分で決められない子どもで悩んでいる親御さんがいたら、一度 頑張ることを手放してみてはいかがでしょうか。
大切なことは、子どものことは子どもにできる限り任せること。
必要以上に提案したり、誘導もしないようにしましょう。
本人が自分の気持ちを話せるような関係、環境が大切です。
時には、その判断が失敗することもありますが、達成感は自分で決めたことの方が大きく、自信となります。
(※もちろん内容によって難しいケースもあります。)
また、決められない子どもは、自分以外の他者の立場に立って物事を考えることに優れています。
チームで協力するような作業は得意な傾向があるので、子どもの得意なことを伸ばし、少しずつ自信をつけていくことで、自分で決められるようになっていくこともあります。