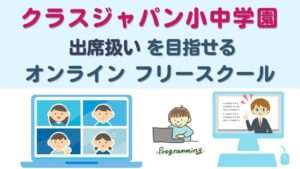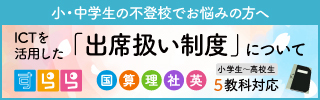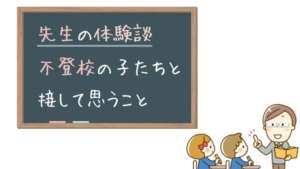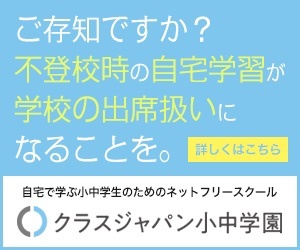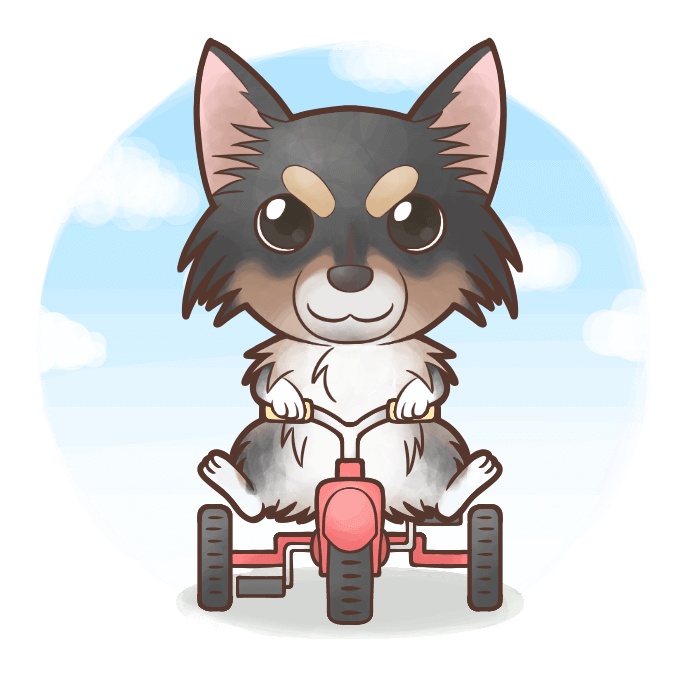不登校の子と関わった体験談|フリースクール、適応指導教室、塾講師
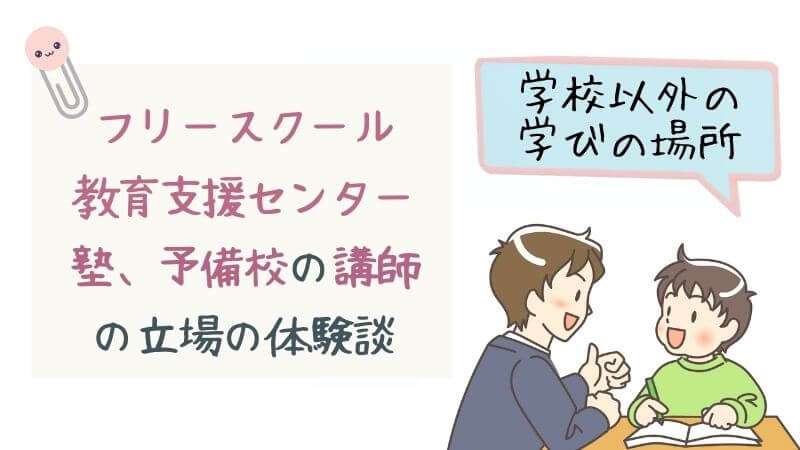
体験談を募集した時に、本人やご家族だけではなくて、先生など不登校の子ども達と関わった方々からも募集しました。様々な視点から、お聞きしたかったからです。
前回紹介したのは、学校の先生(教職員)でしたが、今回は学校以外の学びの場所で関わった先生の体験談を紹介します。
 そら
そら勉強面だけではなくて、子どもが家族以外の第三者の大人と接点をもてる貴重な機会となります。この居場所も探すのが難しいのが現実ですが(行けない子、外に出ることが難しい子もいます)
時には 子どもだけではなく、親の相談相手となってくれることもあります。
ただ、民間のフリースクール、塾はそれなりの費用がかかりますね。不登校となると、現実的にお金がかかります←ここも問題です。
我が家は塾の先生が相談に乗ってくれたことが、親子ともに心強かったです。
(不登校となってから通えなくなり休塾、数か月後に本人の希望で また通い始めました。1人の時間を作ってもらえました)
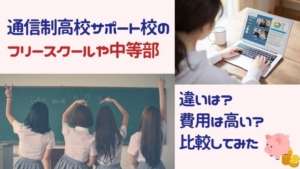
フリースクール、教育支援センター(適応指導教室)
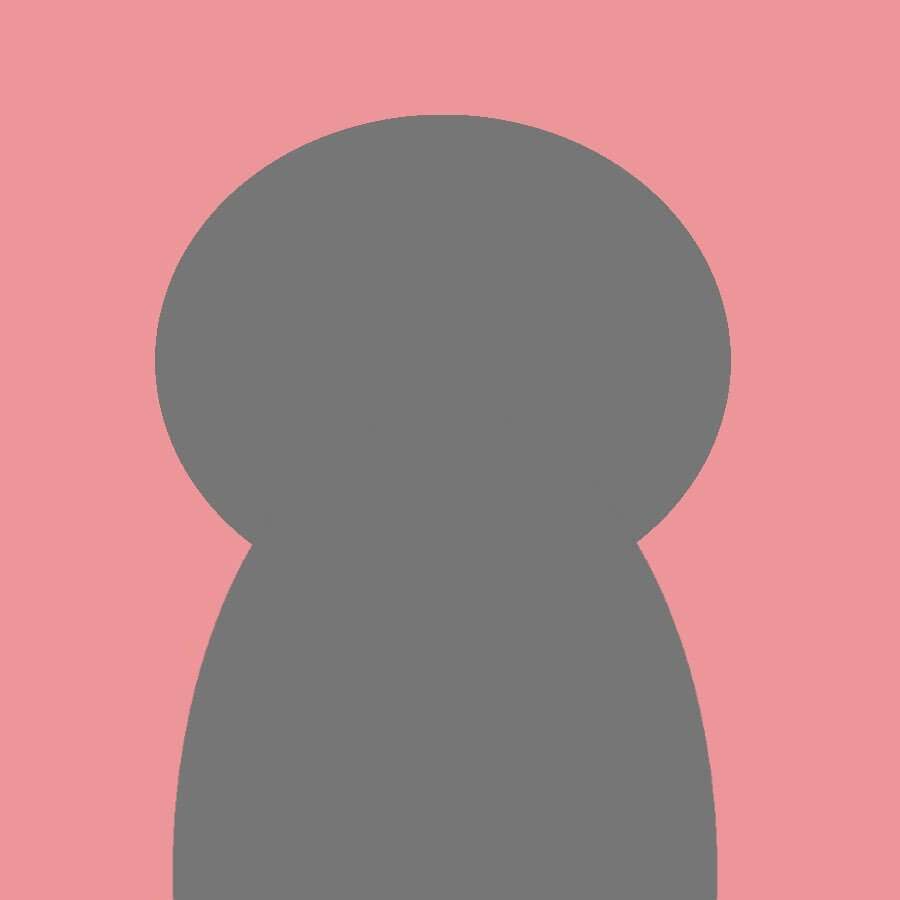
不登校の小中学生が通うフリースクールで週に2日、教科指導を行っておりました。
「不登校」と一口に言っても、不登校になった理由や原因が学校の教師との関係にある子、友人関係にある子、学力にある子、親との関係にある子など千差万別で、それぞれに配慮した対応をすることが難しい点でした。
居場所についても、学校に行きたい思いは強いのに足が動かない子もいれば、学校を拒否する子もいたため、それぞれを認め合う態度や気持ちを醸成することに心を砕きました。
勤めていたのは小規模なフリースクールでしたので教室数が少なく、学校のクラスメイトの乱暴な接し方が怖くて通えなくなっていた子と、発達障害による多動気味の子とが同席するときなどは非常に神経をつかいました。
基本的には、来校する曜日や時間帯をずらして対応していましたが、イベント時などはどうしても重なってしまうんです。
その場合は、お互いの感情や特性を話し、できる限り思いやりを持って接すること、接する時の工夫(少し距離感を保つ・怖いと思ったら離れるなど)を教えて本当に少しずつ、短時間で回復可能な微々たる負荷から経験を重ねるような機会を作ってみたりもしていました。
フリースクールを探してお子さんを連れてくる親御さんは、教育に対して熱心で協力的な方が多い印象です。
ただ、生徒本人と話していると「親から褒められたことない」「友達(兄弟)と比べられる」といった理由で、保護者との精神的な距離感を感じている子もいます。
子どもの「自分を見てほしい、認めてほしい」という思いに大人が気づくことで、不登校の子どもたちが安心し、満たされた気持ちで過ごせる居場所が増えるのではないかと考えています。
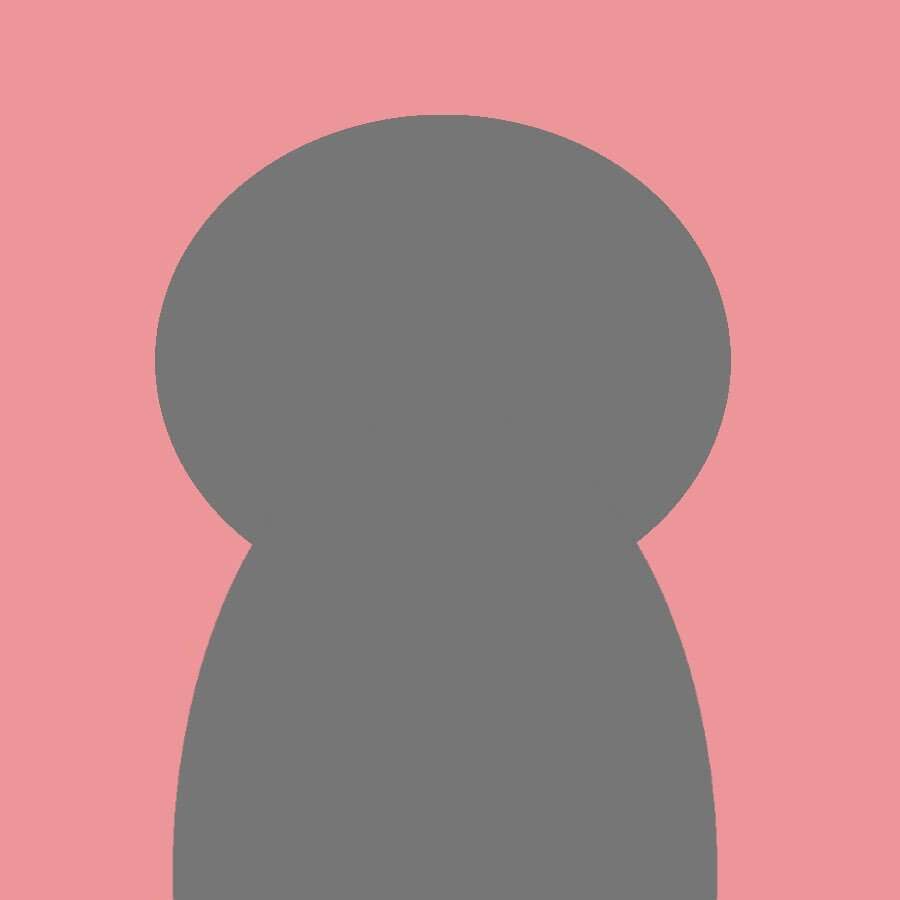
私は、以前 フリースクール等で不登校児童の対応をしていました。現在は発達障がいのお子さんの家庭教師をしております。
発達障害の人の場合、人によっては対人関係で定型発達の人の数倍ストレスを感じることが多く、多くの人はそれを処理できなくて溜め込んでしまう人が多いです。
また、こだわりがあって動けない。あるいは自分の生活のリズムをコントロールできない人も多いです。
不登校になる人は特に、発達障害と定型発達のボーダーラインの方が結構見られます。自分で問題を抱えていると認知していないので、困りごとを感じておらず、ある時一気に出る方もいます。認知の問題が原因の人もいます。
視覚認知に問題があるので授業がわからなかった人もいました。認知の癖があり、それを本人が認知出来ていなかったケースもあります。そういう人は検査機関等でKーABCⅡなどを受けると明確に数値化してでてくることもあります。
スクールカウンセラーは当たりはずれが大きいです。私の実感だと、わかっている人:わかっていない人の比は1:4くらいです。
「この人わかっていないな」と思ったらすぐに切りましょう。時間の無駄です。スクールカウンセラーよりも、各地域の相談機関に聞いたほうが良い対策がでてくることが多いです。
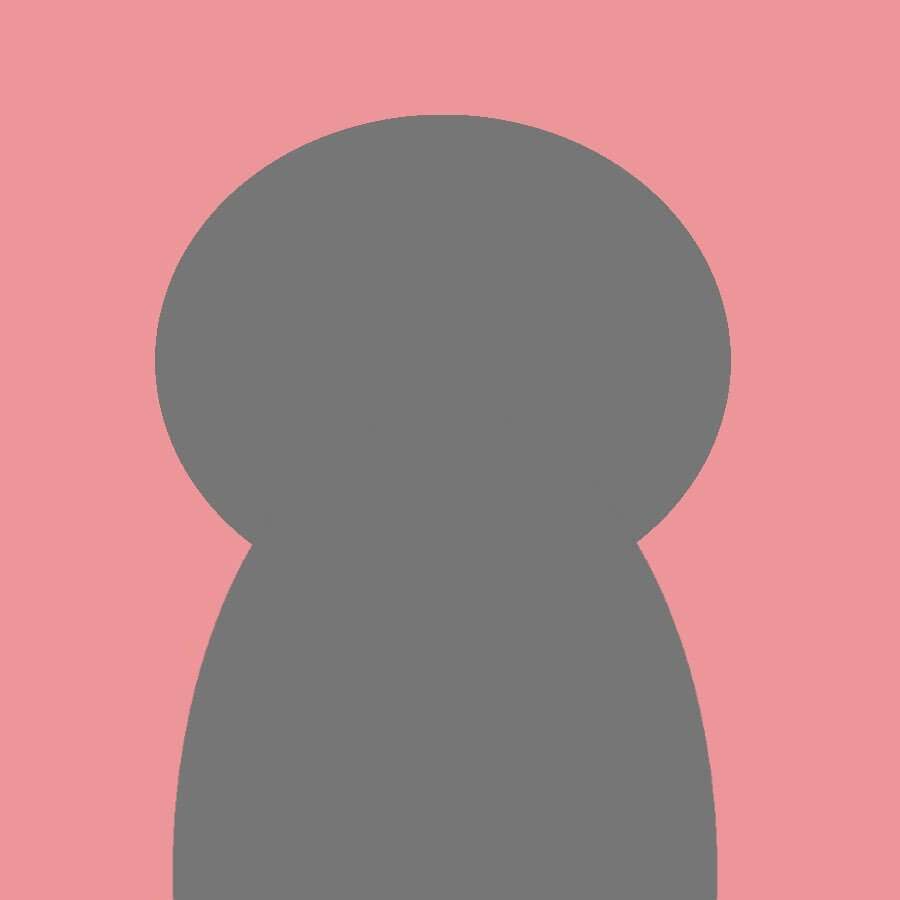
私が不登校児に対応したのは、不登校児が通う教育支援センターです。
教員の免許もあったので、勉強を教えることもありましたが、草むしりや外遊びなど体を動かすことの方が多く、そこを一生懸命やっていると子ども達も信頼してくれて、色々と話をしてくれるようになります。
学校でのいじめを機に不登校になるというイメージを強く持っている方もいるようですが、意外と理由などが明確ではなく、ただなんとなくという子が多いのが現状です。
義務教育のあいだは、あせらないで子どもと向き合うようにしましたが、性格上のめり込んでしまう場合があるので、そこは無償のボランティアという立場を頭に入れ接しました。
親御さんと話す機会があるのですが、やはり綺麗ごとしか言ってくださらない人が多数なのかなと思います。なので、本当の対応が出来ないこともあります。
不登校は恥ずかしいことではないので、包み隠さずに話ていただけると嬉しいです。家族から聞いた話は子どもにしないですし、勿論その逆もしません。
不登校を解消させるための要因が隠されているかもしれないので、しっかり話を聞きます。
そういう場に来てくれる子どもは反抗しようが、黙っていようがまだいいのですが、ピタリと来なくなり、親御さんもそれでいいというとなかなか難しいなと思います。
不登校は、子どもだけの問題ではないので、家族での協力あってです。それを理解してもらって、色々な対応策が生まれると思います。
塾、予備校の講師
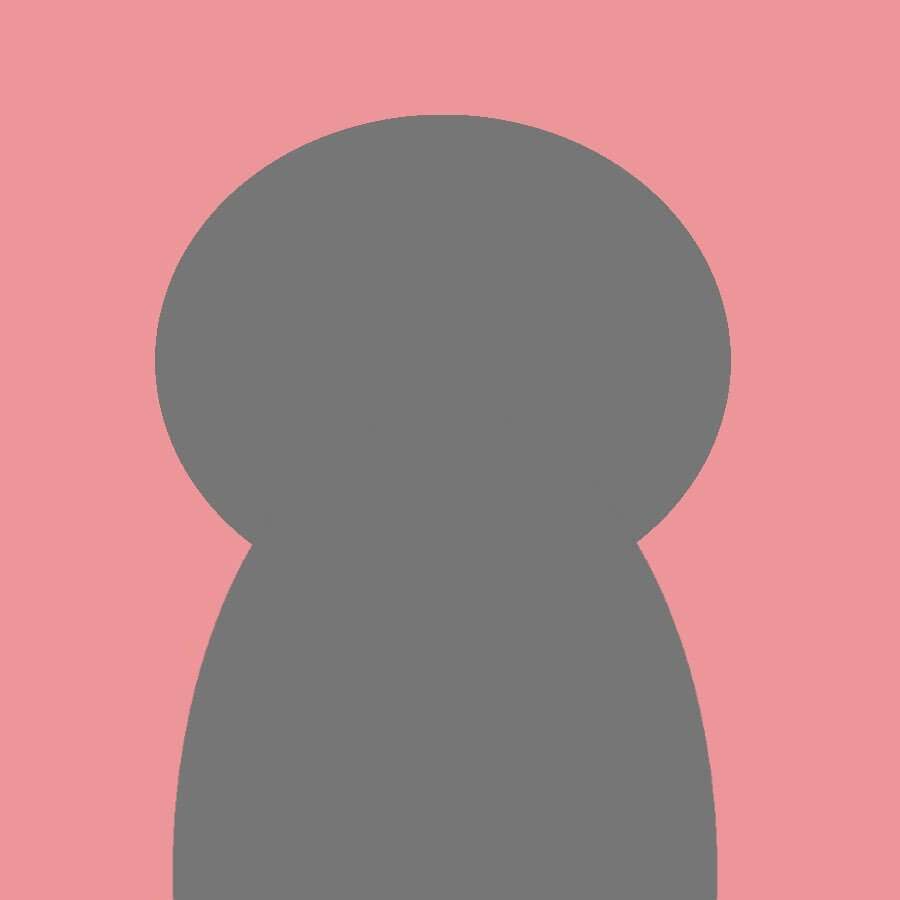
個別指導塾の講師をしているものです。
かつては精神保健福祉士として、障害者のグループホームで働いていたこともあり、現在の講師業においても、生きづらそうな児童を見かければ、福祉的視点で対応することもしばしばあります。
生きづらさは児童に限ったことではもちろんありませんが、少子高齢化や地域に見守りの資源がだんだんと少なってきている現在を考えれば、育っていく環境は過酷といえるかも知れません。
小学校高学年の女子児童を受け持ったときの話です。
一年ほど前から不登校状態になり、学習の遅れを心配した親御さんが個別指導教室にお子さんを通わることになったのが、関わりのきっかけです。
親御さんの話によると、同級生のいじめをきっかけに不登校がはじまったとのことですが、親御さん、特に母親のこだわりの強さ、しつけの厳しさには目に余るものがあり、少なからず娘さんはプレッシャーを感じているのではないかと思いました。
お子さんの将来のことなのでと、親御さんと娘さん本人に了解をとり、学校の担任と通っている児童精神科医のソーシャルワーカーに連絡をとり、意見交換をしたのですが、やはり母親の言動が強く娘さんに影響を与えているのではないかとのでした。
娘さん本人は、塾で母親のことを悪くいうことはないのですが、腕には確かにリストカットのあともありました。
子どもの不調は家庭にも もちろん病理があると考えられることから、娘さんの心のケアは、ソーシャルワーカーが担当し、母親のケアは、月に2回ほど私が時間をつくって母親に話をきくことにしました。もちろん、指導というものではなくあくまで傾聴を心がけました。
話をうかがっているいるうちに、母親自身も厳しい教育を受けてきたこと、自身は専業主婦であり どうしても子どものことだけが気になってしまうこと、自分自身はそれほど厳しくしているつもりはないこと、配偶者との関係がうまくいっていないことなどを丁寧に聴き取っていきました。
一朝一夕に状況が改善するわけではありませんが、児童やその両親をあたたかく見守るチームが重要なのだなと思いました。
個別指導塾の講師としての職分を逸脱しているかもわからないですが、このような対応が必要な家庭が多くあるとの印象をもっています。
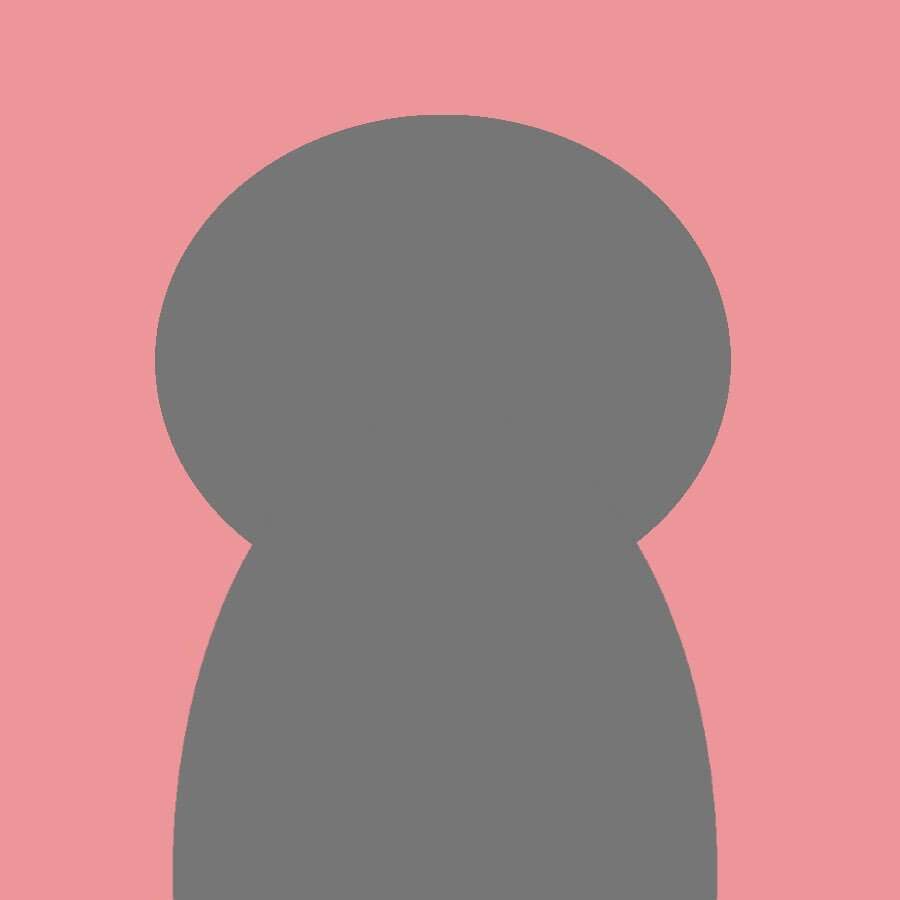
私は予備校でチューター、講師の事務補助をしながら、進路面談や質問対応をしていました。その際、不登校生と接する機会がよくありました。
というのも、私自身高校に通わなかった時期があり、それを耳にした生徒達が、人気な講師やチューターを避けて私に質問をしに来ていました。
今思えば、残念な経歴を隠さない、ある種同類に見える私の方が接しやすかったのでしょう。彼らの性格は千差万別でしたが、厄介な共通点がありました。皆模試嫌いなのです。
誰かと比較され、「ダメな自分」を突き付けられる模試が大嫌いでした。そんな彼らを上手く説得して試験を受けさせるのに手をやきました。
ではどうしたか?
採点の仕方に一工夫いれました。当時、100%方式と名付けた方法です。一旦、偏差値や正答率の計上はせず、1人でテストを受けさせます。その後、私が採点して、あるお願いをしたのです。
「間違えた問題の内、自力で解けた問題と絶対解けなかった問題を仕分けして」とこの問いをして、例えば間違いが10個で凡ミスは0個、他10個なら実力は100%発揮出来ていた。と誉めてあげるのです。
例え30/100点でも、100%を発揮出来ていれば、とにかく手放しで誉めていました。つまり、模試を偏差値という他者との比較ではなく、自身の実力が何%出せたか?という比較に置き換えたのです。
不登校ながら、勉強をしに来た子達ですから、やる気はあります。でも、人と比べられるのは……そう言った子に自信をつけさせるのが狙いでした。
彼らとしては、点数が低くともチューターに誉められるのは嬉しい様子を見せてくれます。そうすると、次は「じゃあ次は120%を目指そう。出来そうな問題ある?」と復習にやる気をださせるのです。
こうして、数ヶ月程した後に、再度同じ模試を受けさせると 当然ですが、点数は上がります。そして、「前と比べて100%上昇、2倍だよ!!」と過去の自分からの飛躍を誉めてあげるのです。
そうして、最後まで予備校に来てくれた生徒は納得のいく進路に進んでくれました。
勉強は点数をつける関係上、どうしても、他者との比較になります。学校を嫌悪する子達には、それがストレスで仕方ないと私には見えました。
そんな彼らが、他者と比較せず、自身の力で、点数を上げていく快感を味わえれば……と考えた褒め方です。
質問者様とお子さまの力になれたか分かりませんが、私自身を含めて不登校時代を含めて、今社会に出た学生は大勢います。お子さまの今後の栄進に少しでもお力になれたのなら幸いです。
その他、講師
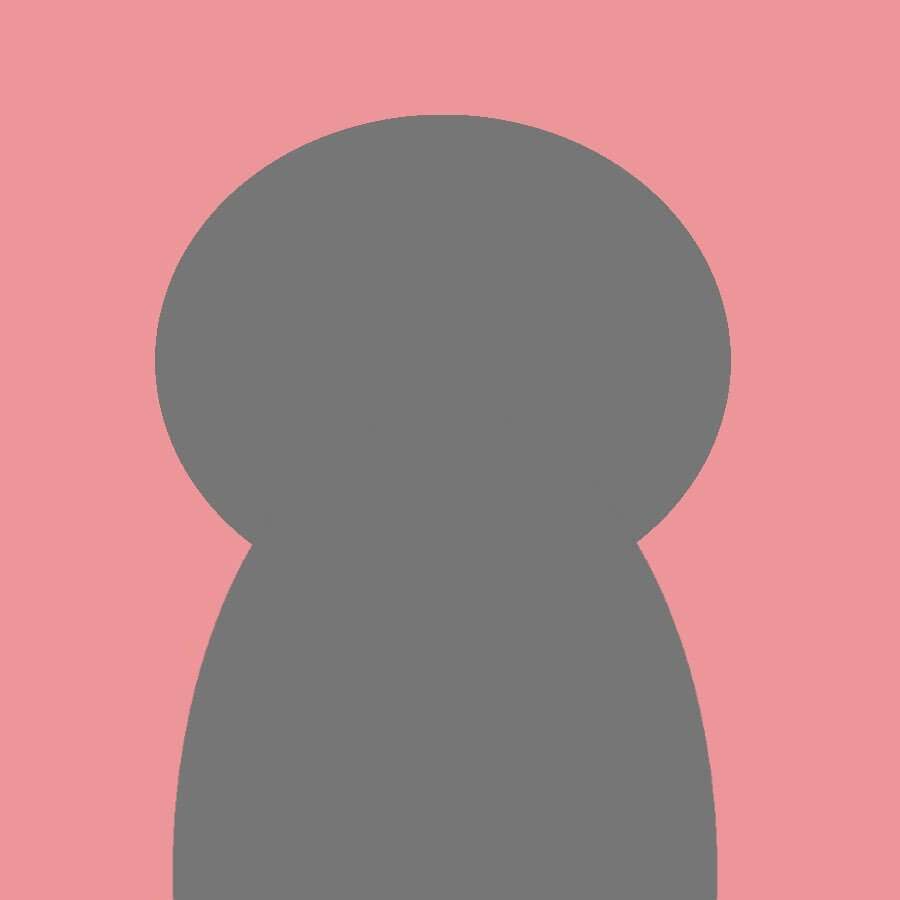
演劇の鑑賞団体が主催する「表現活動のワークショップ」の講師として不登校の生徒・児童を含むグループの指導をしました。
プログラムの中で参加者は表現についての再体験をします。「こんにちは」という言葉一つで様々な意味を伝える、「ありがとう」をつかわずに感謝の気持ちを伝える。
といった単語を使ったプログラムや、言葉を全く使わないプログラム、すべてを単語で説明するプログラムなど様々なメニューがあります。
言葉を発した側の意見ではなく、受け止めた側の意見が重要視され、何度もフィードバックして、そこにいるグループが納得できる結論を導き出すといったことを、基本的には演劇の手法をもちいた楽しい時間の中で再体験します。
参加者のほとんどは一般の学生のグループ、社会人のグループなど大きな分け方で適正な人数のグループ活動を行います。
「表現」と聞いて構える方も多いですが、実際は「日々行っているコミュニケーション」です。
昭和のころとは違い「多様化」が前提の現代において「どのような言葉遣い」「どのような態度」が望まれるのか、誤解を生むのかを実際の体験を交えて考察する時間は、不登校の児童を含む多くの参加者にとって、発見することの多い時間となっているようです。
 そら
そら他にも不登校を経験したご本人、ご家族、また、先生など関係者の方々の体験談を多く紹介しています。
今はオンラインのフリースクールもあります。