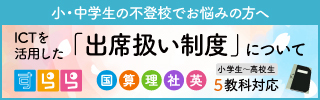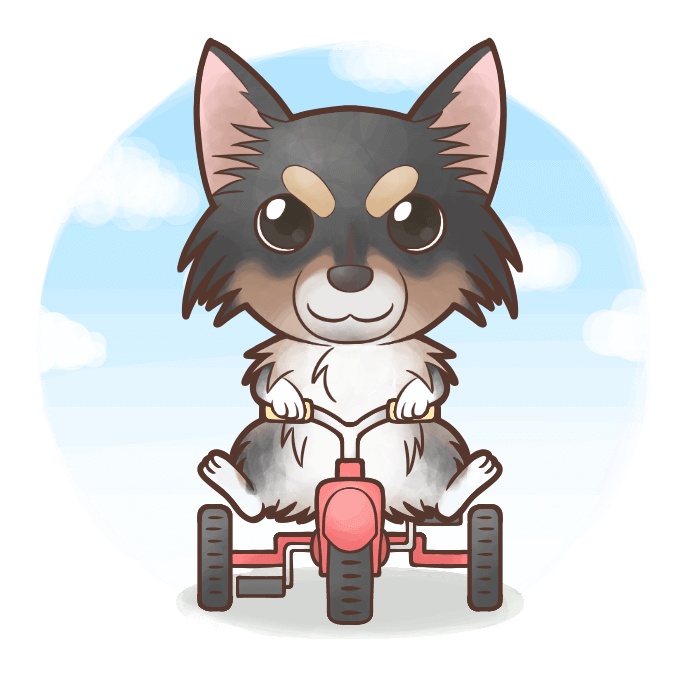体験談|不登校支援、ボランティアで子ども達と接して感じたこと

募集した中に、先生の立場(学校、フリースクール、塾、家庭教師など)、学習支援だけではなく、ボランティアとして不登校の子ども達と関わった体験談がありました。
 そら
そら年齢が近い学生の場合、また感じ方が違うんですよね。
子どもに近い目線で語ってくれています。
この記事では、ボランティアとして活動された方の体験談を紹介します。

メンタルフレンドって知っていますか?
訳すと「心の友」ですね。
不登校、ひきこもりの子を支援するボランティアで自宅に訪問してくれます。
各自治体で募集しています。知っておくといいですよ。
東京都の例
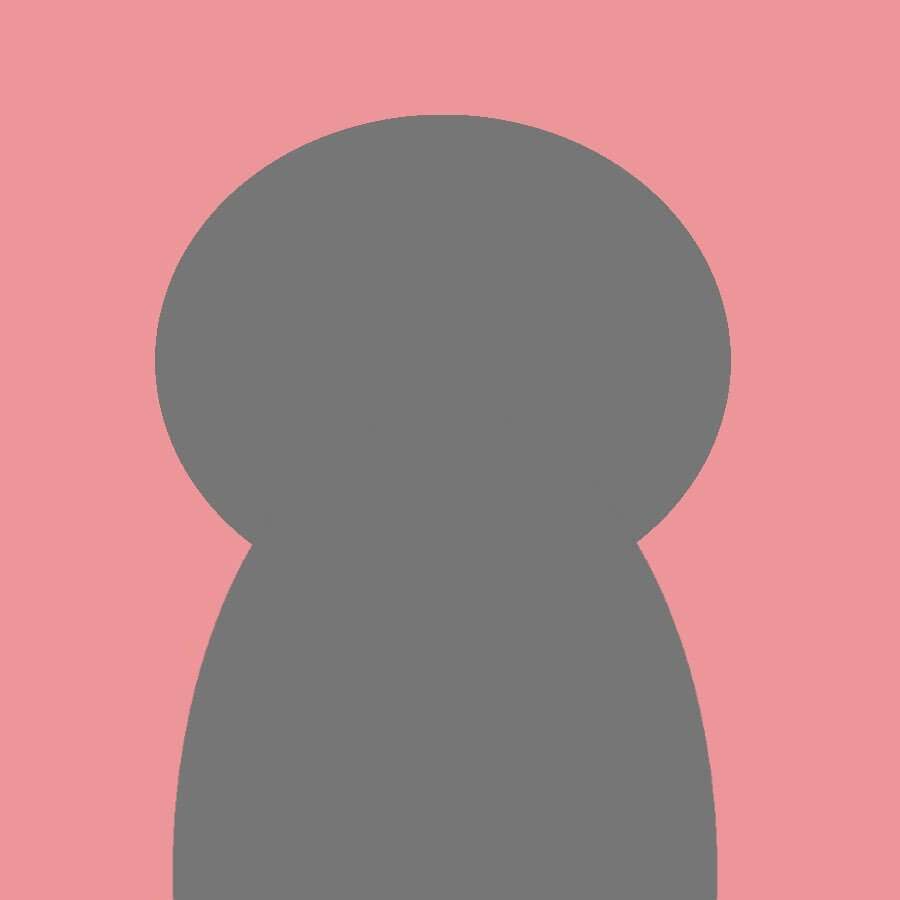
自分は高校在学時、小学生の不登校児の相談相手として母校に呼ばれて ちょっとした相談相手をしていました。
というのも自分自身が小学生時代に不登校になっていたこと、他の不登校の子を連れて遊んでいたことで対応が上手いのではないかと思われたことがきっかけでした。
不登校の子にはそれぞれ異なる理由がありました。そしてそれは大概、親にもましてや教師の方にもにはあまり分かってもらえないものでした。
大人の人たちはよく言います。社会に出たらそんなのは通用しない。僕も26歳になった今、その言い分も理解しています。
しかしちょっと考えましょう。それ、大人以外に関係ない話じゃないのかと。子どもにとっては今が全てです。
少し極端な言い方になるかもしれませんが、ほとんどの子どもはその日に何があったか、何が起きるのか、今日までの間に何があったのかだけが気になっています。
朝ごはんはなにか、給食はなにか、晩御飯はなにか。極端に言えばこういう感じで思考しています。
そこに過去の体験やその日その日の出来事が乗っかっているだけです。年齢が上がるに連れて体験は増えていきます。それを処理するだけの頭や心が伴っているかと言われれば正直微妙でしょう。
怒られたり、泣いたり、喧嘩したりするのが子どもで、それらの印象は子供にとって強烈に頭に残っています。そうやって色々なものに疲れた結果が不登校に繋がるのです。
にもかかわらず、「お母さんはこうだったけど大丈夫だった」とか「世の中にはもっとつらい思いをしている子だっている」、「大人になったら通用しない」などという大人が数多くいます。
教師に言われるのならまだ耐えられるかもしれませんが、親御さんにこんなことを言われたら子どもは大人を信用しなくなります。
自身の体験を話すことは、けっして悪いことではありませんが、それは寄り添ってからしてあげるべきことであり、頭ごなしに子どもが今感じていることを否定する行為になってしまいます。
私が対応するうえで気をつけていたことは、本当に基本的な2つのことでした。
1つ目は自分がされて言われて嫌なことはしないことです。これは当たり前で、先生方も親御さんもケンカの仲裁でこれを言いますが、私からするとそれを最も守れていないのは言っている本人たちです。
例えば、しつけで晩ごはん抜きという方がいたとします。これを大人に変換すると今日の君の給料ゼロねと同じことです。子どもには給料が存在していません。
生きることが仕事といえば仕事になるのに、悪いことをしたから晩ごはんを抜くという行為は、失敗を自らの給料で補填させる行為です。とんだブラック企業です。
実行するかどうかは問題ではありません。問題は『逆らえない下位者に対して、権限を持った上位者がそれを言った』という事実です。大人の社会ではパワハラ、またはモラハラに該当する行為です。
何気ない言葉ですが、先ほど書いたように子どもはとても単純な思考をベースに日々を生きています。なのにベースに影響を直接及ぼされ、心に傷を負ってしまったとしたら果たしてそれを責められるのでしょうか?
ですから 私は子ども達と接するときに強い言葉を使わないように気をつけていました。ダメなことはダメだと教えるけど、何かを取り上げる罰は与えませんでした。かわりにやるべきことをやったら褒めていました。
廊下を走るなと教えて走らなければ褒める。ケンカしたとき、謝れれば褒める。そんなささいなことでしたが、ささいなことが最も重要なのです。なぜならそんなささいなことを大人は気にしなくなるものですから。
ささいなことだと切り捨てるのは、いつでもできるのでまずはひろってあげましょう。文句はひろえてから言うことが大事です。
2つ目は話を聞いて、返せる答えは返すことです。基本ですが、これもおろそかになりがちな部分です。
先生方は1クラス何十人も見ていますので全員を気にすることは不可能でしょうが、残念ながら子どもはそんな事情を知りません。
子どもは大人になったら、自分が今できていることの10倍くらいできると割と本気で信じています。要は期待されているのです。子どもにとって大人はいわば巨大な本です。
知らないことを知っていて、いろいろなところに行っている存在なのです。だから色々聞いてきます。
何でその仕事に就いたのか。昔の将来の夢は何だったのか。お父さん、お母さんはどんな子だったのか。建物を見てあれはなんだ。電車を見てあれはどこに行けるのか 等々です。
子どもにとって、聞く・答えが返ってくる というのは自分のことを考えてくれているという大きな証明になっています。
自分の分からない質問でも調べて、後日に答えを返すととても嬉しそうにしてくれました。どんなにくだらないと思える質問でも、それを否定しないであげることが大事なのです。
しかし、学校はそもそも大多数の人間の中で何かを否定する場所です。その考え方はよくない、ああしたほうがいい、こうしたほうがいいと教える場所です。
ですので、質問を自分で調べてと言って閉ざしがちですが、相手の家庭環境次第では傷つける結果になってしまいます。
最後になりますが、そもそも不登校自体を悪いことだと私は思っていません。自分にてらしあわせても、接した子たちにてらしあわせても、そのまま無理に行かせることのほうがつらい結果になっただろうと今でも思えるからです。
頑張れてしまう子もいますが、その子と比較して あの子は頑張ってるんだからというのもやめてあげてください。
どの子も自分の中で色々フタをしたり、切り捨てたりして前に進んでいるのだということを忘れないであげてください。
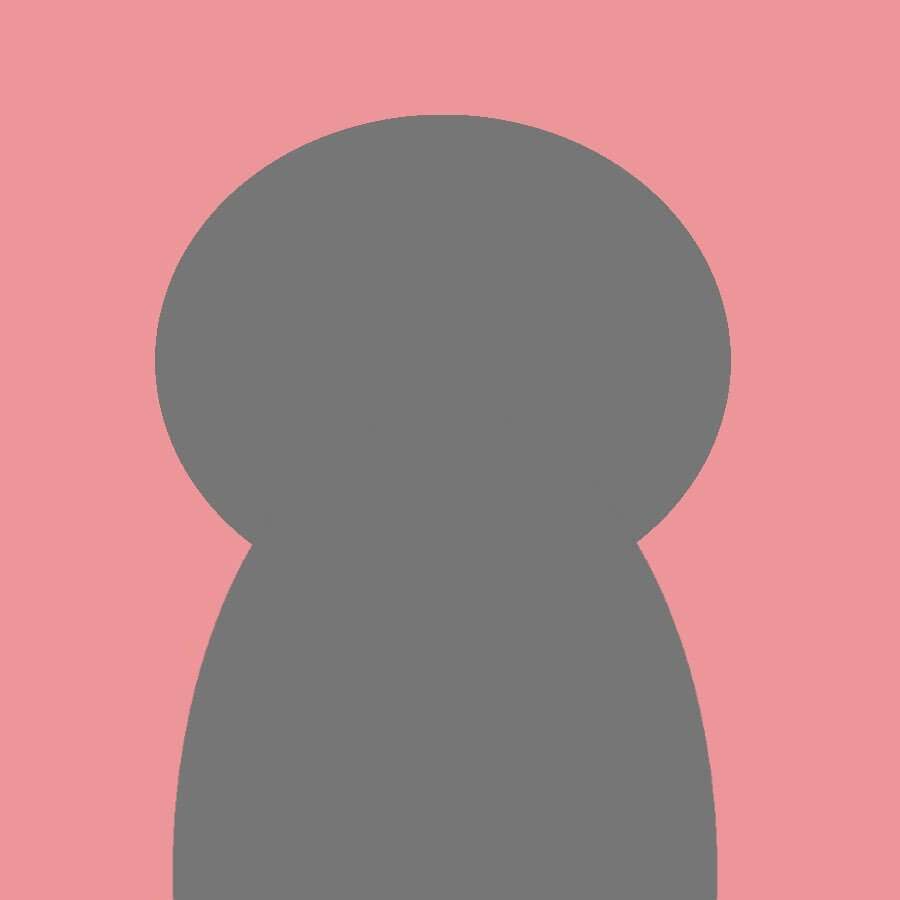
不登校の小学生のボランティア経験について紹介します。
私は高校生で相手の子が小学生でした。週に1回、手芸やお絵かきなど図工のようなことをしました。
苦労した点は会話のきっかけを探すことでした。学校に関することは聞かないでほしいという事前の要望があり、趣味について話など工夫をこらしました。
作品を作っている最中は「この柄かわいいいね。」や「鳥のモチーフが多いけど、鳥が好きなの?」など、作品について、積極的に声かけをしました。
はい、いいえなどのクローズド・クエスチョンから数回会話をして、緊張を少しほぐした後、オープン・クエスチョンに話をもっていくように心がけました。
気分によって話しかけてほしくない日もあったので、よく観察しながら会話をしました。笑顔で話してくれたときがとても嬉しかったです。
不登校の子どもの増加については、今まで確認されていなかっただけで もともと多かったのではないかと考えます。
不登校の存在が顕著になりメディアに取り上げられるなどし、存在が把握されるようになったためもあると思います。
不登校の子どもには、繊細な心の子や自分の気持ちを上手に伝えられない子が多いと思います。
専門の知識をもった方や、人生経験が豊富で価値観が柔軟な方が対応にあたり、支援の方法が増えていくことを期待します。
震災後の、子ども達の心のケアに関わった体験談です
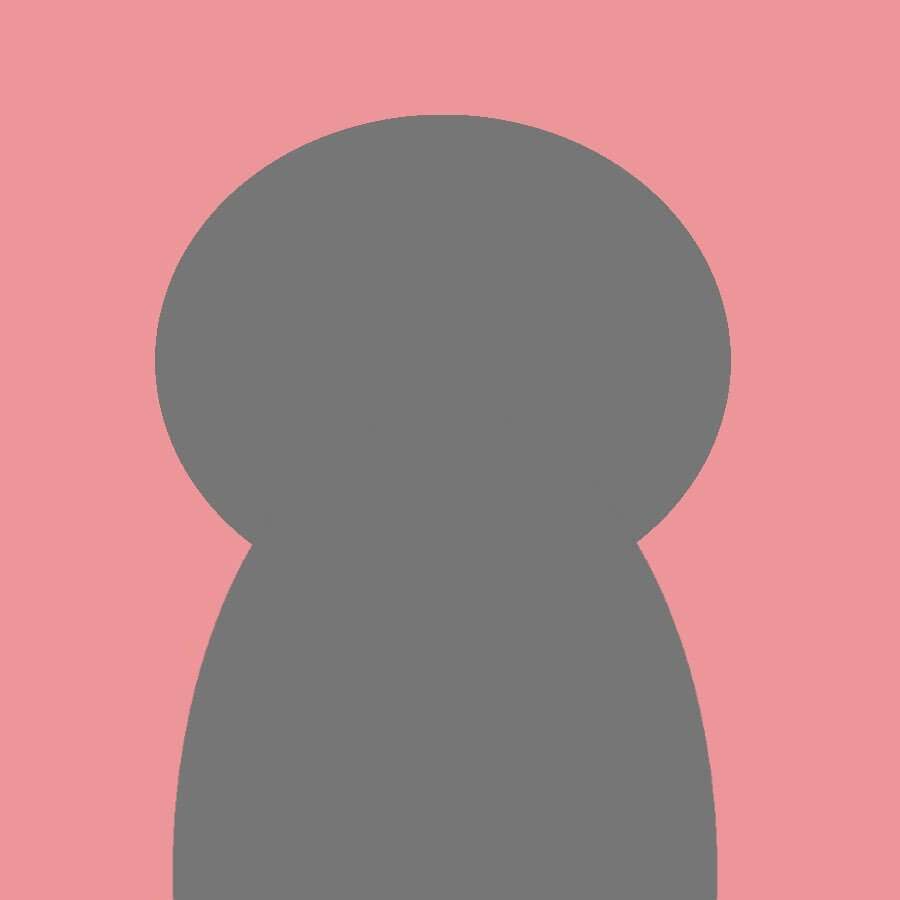
私は、東日本大震災後に某団体職員として相談員の仕事をしていました。
私たちの仕事は性別も年齢も被災したかどうかも関係なく、困った人のもとへ急ぐといった感じです。その中で、不登校の児童にはたくさん出会いました。
両親を津波で失ってしまった悲しみや、コミュニティの変化についていけずに不登校になってしまったり、理由は様々ですが、対応が難しかったのは事実です。
まず、会ってもらうまで通いつめて、話をしてくれるまで待ちます。学校に行かないことは責め立てず、見守るだけというパターンが多かったです。
学校の先生や市役所の職員も訪問し、原因を理解したうえで「来たかったら来て」と保健室やカウンセリング室の窓やドアを開けっぱなしにしていました。
学校に通っている子どもでも、スクールカウンセラーの部屋までしかいけないと聞いていたので、悲しい話もせず、昨日見たテレビの話や好きなペット、好きな歌手の話など「特別な子」としては見ないで雑談したり、公園で一緒に遊んだりしました。
次第に学校へ行く児童もいましたが、中学校の卒業式にも出席せず、未だに不登校の子もいます。
震災の傷は、元気そうに見える子どもたちでも時々かんしゃくを起こしたりするので、まだまだカウンセリングなどが必要だと感じます。
 そら
そら他にも不登校を経験したご本人、ご家族、また、先生など関係者の方々の体験談を多く紹介しています(当サイトで募集しました)