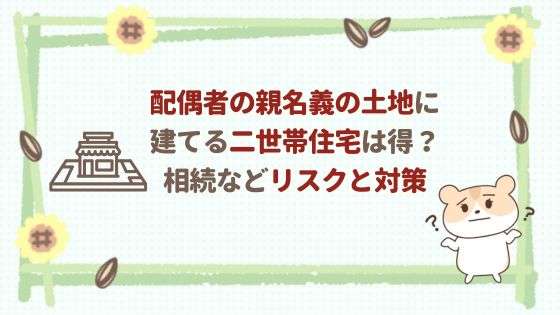記事内のリンクは一部広告を含みます
二世帯住宅の土地探し、後悔しないための7つのチェックポイント
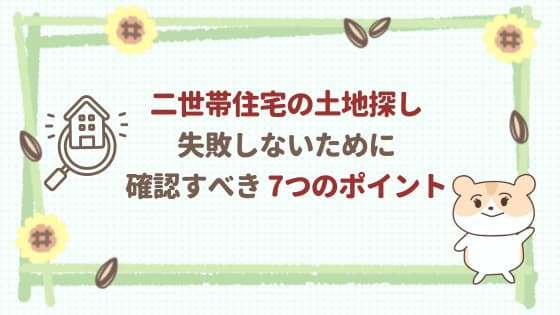
我が家は、もともと土地があったわけではありません。
義父母、私達夫婦は賃貸マンションで別々に暮らしていました。
なので、まず土地探しからスタートしました。
 なつお
なつおこの、土地探しが一番時間がかかったよね…。
 なつか
なつかほんとに。いくつもの候補地を見学したよね。
二世帯住宅を建てるうえで、最も重要とも言えるのが『土地選び』
お互いのライフスタイルを尊重しながら、快適に暮らせる住まいを実現するには、家づくり以前に最適な土地を見極める必要があります。
…と言われても、知識がない あの頃は大変でしたね。
ハウスメーカー・不動産会社の方に相談したり、自分達でもかなり調べました。
結局、我が家は独立行政法人都市再生機構(UR)の土地に応募。
1回目の抽選は落選⇒ 2回目で当選した土地に建てました。
この記事では、二世帯住宅を検討中の方が土地選びで失敗しないために知っておくべきポイント
について書きます。
 なつか
なつか20年前と違い、今はオンラインで情報が集めやすくなりました。
自宅から一括で最新情報を得られ、比較することも可能です。
\二世帯住宅にぴったりの土地を探そう/
【無料】ネットで土地情報を一括請求する
>> 土地探し特集
Contents
はじめに|妥協できない点と優先順位を考えよう
二世帯住宅の土地探しは「家族の将来設計」を考える必要があります。
まず、家族全員の、これから の希望を聞くことが大切。
もちろん、希望が多くなればなるほど難しくなります。
なので、妥協できない点、優先順位を明確にしましょう。
 なつか
なつかポイントを7つに絞って説明しますね。
1.ライフスタイルの違いを尊重した立地選び
二世帯住宅で大切なのは、「お互いに心地よく暮らせる距離感」をつくること。
そのためには、親世帯と子世帯の生活スタイルの違いをしっかり理解することが第一歩です。
親世帯
子世帯
親世帯の年齢や健康状態、就業状況にもよるでしょう。
また、子世帯の家族構成・子どもの年齢も関係してきます。
かかりつけ医、学校関連、スーパー、通勤に使う駅などは確認が必要です。
生活スタイルの違いを把握した上で、どちらか一方に偏ることなく、双方の満足度を高める立地選びが大切です。
 なつか
なつか嫁の立場だと言いづらい部分もあるよね。
第三者(専門家)がいる時だと伝えやすいですよ。
また、高齢になると免許を返納する時がきます。
義母は、スーパーの往復ぐらいでしたが、80歳になる前に運転をやめました。
今は、私と夫が運転、もしくは自治体、市の運航するバスを使っています。
高齢者の移動手段、助成制度が助かります。
公共機関の利用、車を持たない生活も想定した環境が理想的です。
福祉センターも近くにあるといいですね。
2.建築可能な土地か?用途地域と建ぺい率・容積率の確認
二世帯住宅は「広さ」が必要ですが、建ぺい率制限により、希望するプランの間取りが実現できないことがあります。
親世帯と子世帯に、それぞれ生活空間を用意しようとすると部屋数が増えます。
設備が倍になれば、それなりの面積が必要です。
我が家は、上下の完全分離二世帯住宅を建てました。
2階に玄関(外階段)、水回り(キッチン・洗面所・トイレ)、リビング・ダイニングが2つです。
我が家の場合は、購入した土地は223㎡(約68坪)、建ぺい率60%。
当初予定より広い土地を郊外に購入しました。
構造スタイルによる建ぺい率の影響
- 1階に広い空間が必要な場合
→ 建ぺい率の制限に引っかかり、希望の間取りが実現できない可能性あり - 左右分離型(二棟が横に並ぶような形)を希望
→ 横に広くなりやすく、より多くの敷地面積と高い建ぺい率が必要
建ぺい率の注意点
- 建築地域によって違う
市街地では60~80%、郊外や住宅街では40~50%程度が一般的。 - 庭や駐車場も考慮する
建ぺい率に余裕がないと、駐車場や庭スペースが確保できなくなる。
まずは、希望の二世帯住宅のスタイルと建ぺい率と容積率、駐車場の確認をしよう。
車での移動がほとんどになる郊外の場合、車がそれぞれに必要となります。
我が家は、義父が仕事をしていた頃は、義父と夫が通勤用に1台ずつ。
私と義母の生活用に1台の、計3台分の駐車場が必要でした。
実家(二世帯住宅3階建て)は、市街地で駅が近く、親世帯は運転しないので1台(駐車場は2台分)
 なつか
なつか世帯を合わせて、車が何台必要かによって駐車場のスペースが変わります。
希望を伝えて、プロに相談しながら決めていくのが おすすめです。
\ 無料でネット一括依頼!プロがサポート /
3.上下分離?左右分離?構造の特徴と土地形状選び
二世帯住宅のスタイルは、大きく分けて2つのパターンがあります。
共有型と分離型で、完全同居・部分共有(一部共有)・完全分離など、さらに分かれます。
土地が広く必要になるのは、設備が2つずつ必要となる完全分離型になります。
さらに上下と左右に分かれるタイプがあり、土地の形状が変わってきます。
 なつお
なつお1階の建築面積が広くなれば、それだけの土地が必要となってくるということですね。
また、二世帯住宅の場合、建物を一つ、もしくは二つとみなすかにより、固定資産税の住宅用地の特例(軽減措置)や課税区分が変わってきます。
 なつか
なつか税理士や司法書士に相談するのがおすすめ。
自分達で調べるより、プロに聞いた方が早いです。
上下分離と左右分離の比較
上下分離型(二階建て構造)
左右分離型(横並び構造)
上下の分離タイプで、玄関を別につけることもできます。
我が家は、外階段をつけて、2階に玄関をつけました。
実家は3階建ての二世帯住宅で、1階が親世帯、2・3階が子世帯。
1階に玄関が2つ並んでいます。3階建てであれば、土地は少なくすみます。
どちらも、1階の階段を上がる前に扉をつけています。
一つ屋根の下で、この扉一枚で繋がっている形ですね。
 なつか
なつか二世帯住宅の構造と土地条件は、必ずセットで考えましょう。
他にも注意したい点や土地の場所によるメリットを書きますね
土地の形と配置の関係・間口や駐車場について
- 正方形や間口の広い整形地は、建物配置の自由度が高い
- 間口が狭く奥に長い「旗竿地(はたざおち)」では左右分離型は難しい
駐車が苦手な人にとって「土地の形状」や「道路の状況」は非常に重要なチェックポイントです。
安心して、スムーズに車を出し入れできるかどうかは日々のストレスに直結します。
 なつか
なつか私が、ペーパードライバー歴15年だったんですね…。
郊外に引っ越してから運転を始めました。
駐車が苦手な人が意識したいポイント
- 前面道路の幅に余裕があるか
幅が狭いと、何度も切り返しが必要。
6m以上あれば余裕を持って駐車できる。 - 間口が広く、車をまっすぐ入れられる形状か
旗竿地や奥まった土地は駐車が難しい。
できれば道路に対してまっすぐ出入りできる「整形地」が理想。 - 並列駐車が可能か
縦列駐車は苦手な人にはハードルが高い。
複数台駐車する場合は、1台ずつ出入りできる「並列タイプ」を。 - 角地や前面に余裕がある土地
道路が2方向に接している角地は、車の切り返しや転回がしやすくおすすめ。 - 電柱や塀、段差の位置も要チェック
意外と見落としがちなのが、出入口の電柱やブロック塀の位置。
視界やハンドル操作を妨げる位置にあると、毎日の駐車がストレスに。
 なつお
なつお図面だけでなく現地へ実際に車で行ってみよう
南向きの土地のメリット・注意点
- 日当たりが良く、リビングや庭を明るく保ちやすい。
- 家庭菜園が趣味の場合は最適。
- 窓やフェンスの配置でプライバシー対策が必要になる。
 なつか
なつか日差しは心にとても影響します。
精神疾患を抱えている家族がいるなら特に。
娘が不安障害で、南向きで本当に良かったと思ってます。
角地のメリット・注意点
- 道路に2方向接しており、玄関や駐車場の配置がしやすい
- 建築の自由度が高く、採光・通風にも優れる
- 土地価格が割高になりがち。
建ぺい率の制限が緩和される場合もあり(確認が必要)
 なつお
なつお土地の抽選で、倍率が高かったのは南側と角地。
特に、南の角地は激戦で、価格も高くて手が出せませんでした。
\ 無料でネット一括依頼!プロがサポート /
4.プライバシーと共有空間、間取りを意識した土地選び
玄関やキッチン・浴室などの水回り、リビングを共有するか、別にするかによって、土地の広さや形状は変わってきます。
洗濯ものを干す場所、庭の配置にも配慮が必要です。
あとは、音問題。これ、すごく大事。
お互いの生活音が気にならないような距離感を保つ工夫も重要なポイント。
特に、上下の完全分離型の場合、2階の子世帯の音が1階の親世帯に響くんです。
義母は耳が良くなくて、そこまで気にしなかったのですが、義父はうるさいって言ってました。
娘が赤ちゃんの頃、夜泣きがひどくて、仕事で朝が早いのに連日起こしてたんですよね。
友達が遊びに来て走り回った時も、私が気をつかいました。
いくら孫が可愛くても、限度があるんですよね。
 なつか
なつか我慢が続けばストレスになります。
間取りの配慮と防音対策は必要です。
5.将来の相続や売却も見据えたエリア選定
いずれ相続が発生することも視野に入れ、資産価値が下がりにくい場所を選ぶ。
将来売却する可能性を考えて、需要の高いエリアを選ぶほうが賢明です。
駅近や再開発が進むエリアなど、将来的にも価値が期待できる立地を検討しましょう。
 なつお
なつおなかなか先のことを考えるのは難しいけれど、できるだけ情報収集をしよう。
二世帯住宅は売却しづらいですが、広めの土地には価値があります。
6.周辺環境と治安・スーパーや病院など生活利便性
徒歩圏にスーパーや病院、ドラッグストア、コンビニ、郵便局などが揃っていれば、日々の暮らしが格段に便利になります。
特に親世帯にとっては病院の距離が重要な要素。
車がなくても行けるか、公共交通機関や自治体の支援制度があるかどうか。
ないと、子世帯の負担が増えることになります。
子どもが小さい時は、保育園、公園や児童施設なども近くにあるといいですね。
また、夜間の街灯の有無や周辺の治安も現地でしっかり確認しましょう。
忘れてはいけないのが、自治会や町内会、子供会などのコミュニケーション。
(義務じゃなくても、加入があたりまえの地域も多いです)
また、自宅前の道路が抜け道になると、交通量が増えます。
生活道路の通り抜け問題ですね。
いくら南側を購入しても、カーテンが開けられなければ日差しが入らず暗いです。
防犯面やプライバシーが保たれるかは大切です。
 なつお
なつお時間帯を変えて、何度か候補地に訪れるといいよ。
\二世帯住宅にぴったりの土地を探そう/
【無料】ネットで土地情報を一括請求する
>> 土地探し特集
7.ライフライン・地盤・災害リスクのチェック
上下水道や都市ガスなどのライフラインが整っているか、地盤がしっかりしているかも土地選びでは見逃せません。
宅地分譲のまとまった地域でも、場所によって地盤の状態が違いました。
地盤調査の結果次第では地盤改良が必要となり、大きな費用がかかるケースもあります。
また、災害リスクが少ない土地を選ぶことも安心して暮らすためには大切です。
ハザードマップを確認し、浸水や土砂災害の危険がないかも事前にチェックしましょう。
まとめ|二世帯住宅に最適な土地とは
これだけのポイントを全ておさえることは正直難しいです。
でも、最低限、これだけは譲れないポイントがあるはず。
家族全員のライフスタイルや将来を見据え、しっかりと時間をかけて土地を選びましょう。
揉めたくない気持ちもわかりますが、その後の暮らしを考えたら、しっかりと伝えたほうがいいです。
 なつか
なつか担当者に間に入ってもらいながら、うまく話し合いをすすめていくといいよ
 なつお
なつお二世帯住宅に詳しい担当者だったよね
 なつか
なつかそう。だから、いろんなアドバイスがもらえた。
ハウスメーカーもそうですが、二世帯住宅に強い会社、担当者がいいです。
ここからは、我が家の場合なんですが…(さらっと聞いてね)
もちろん、上記のポイントをおさえつつなんですが直感も大切。
は?ここで直感?って思うかもしれませんが、これが あなどれないんですよ。
 なつお
なつお家族みんなが、ここは…なんか違うと思う土地。
逆に、見学した瞬間に ここがいい!って思う瞬間があったよね。
 なつか
なつか最後は、家族みんなが「ここに住みたい!」
そう思う気持ちが後押ししましたね。
明るい未来が想像できる土地を選びましょう。
\ 無料でネット一括依頼!プロがサポート /
にこすまいる
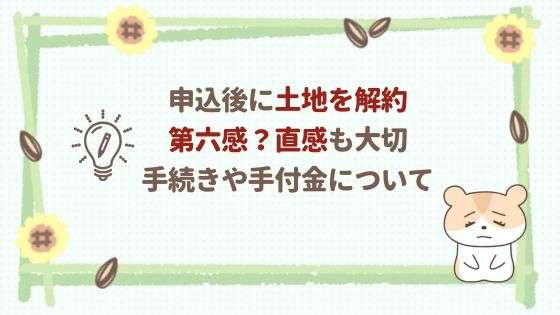
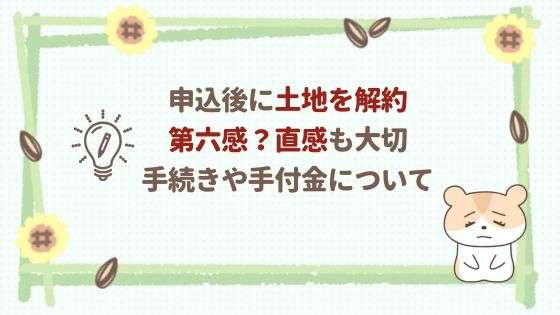
直感は大事|申込した土地を解約した体験談、手付金はどうなる? | にこすまいる
この記事は土地を探した時の話です。我が家は、土地選びに かなり時間がかかりました。 実は、申し込みまでして解約した土地があります。最後にどうしても踏み切れなかった…